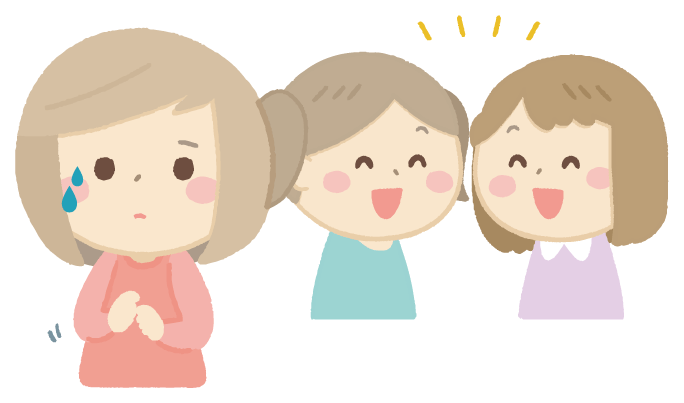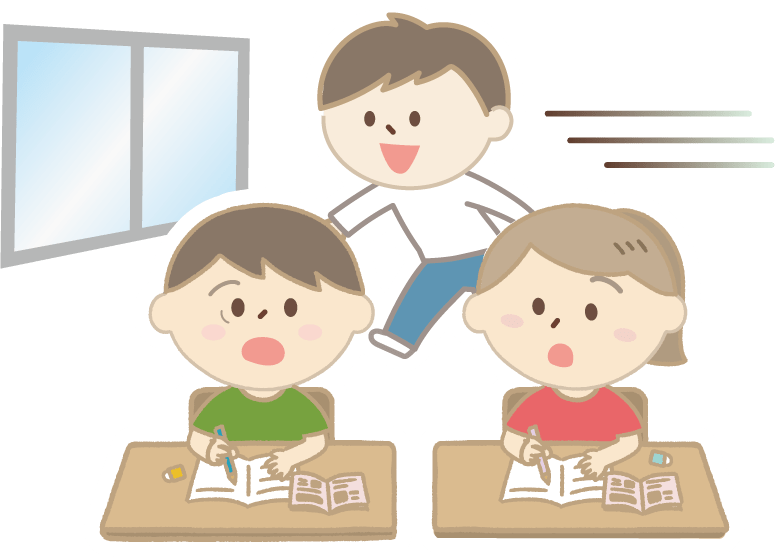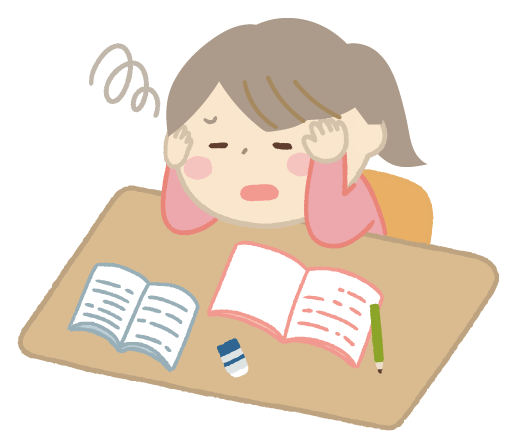発達障害について
- Home
- 発達障害について
「発達障害」とは
発達障害は、生まれつきの特性で、脳機能の発達が関係する障害です。
発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD(注意欠如・多動症)、学習障害(LD)、チック症、吃音などその症状は様々です。同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ重なり合ったりもしますが、優れた才能を持っている場合もあります。
発達障害の特性があっても、小さい頃から周囲の人に理解されて育った子どもの中には、精神的に安定した状態で子ども時代を過ごし、成人になって自立した生活をおくり、幸せな人生を歩んでいる人もいます。一方で小さい頃から、できないことに叱責を受け、否定され続けた子どもは強い劣等感を抱いて、そのまま大人になり、ひきこもりなど、社会に適応できなくなり、つらい状況にいる人もいます。
ですから、発達障害の特性を早期に理解し、療育(発達支援)をしながらその特性をやわらげて子どもの成長を促すことがとても重要となります。
本事業所では、目から入る情報の優位性を活かし、生活全般に見通しを付け自分の行動を予定化(スケジュール化)出来るようにしています。「次の行動を見える化、予定化することで安心を提供し不安なく過ごし、周囲の状況把握と自身の判断力を養い、自己肯定感を高められる」ように支援します。